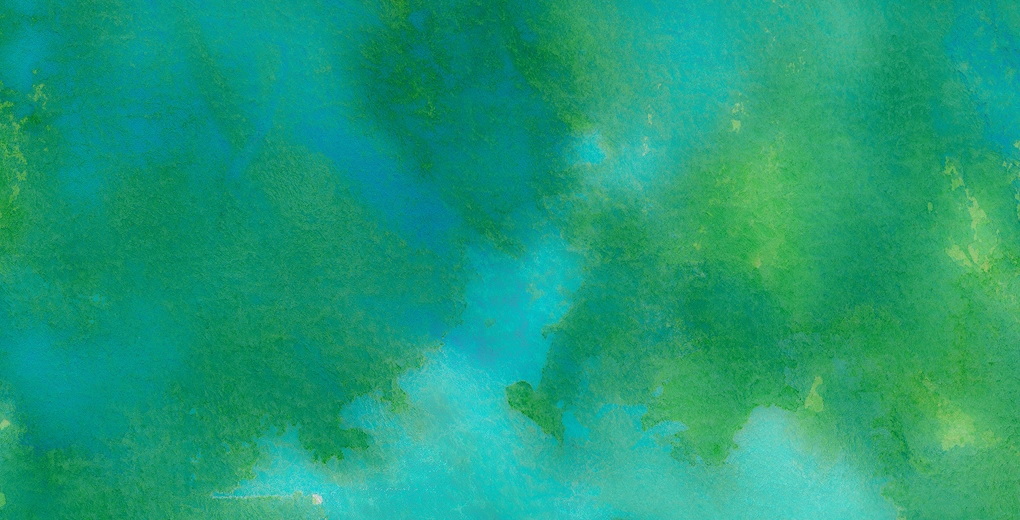「野菜の生育がよくない」「化成肥料の使い方が不安」「どの肥料を選べばいいか分からない」……そんなお悩みをお持ちの方向けに、畑の土づくりと肥料の“基礎のキソ”を、一から一緒に学び直しましょう。
仕組みを理解して実践すれば、畑が見違えるように変わるはずです。
- この記事のポイント
- 用語解説
- その肥料の使い方で大丈夫?畑の土づくりを見直そう
- 【第1章】土づくりの基礎|肥料の定義や種類とは?
- 1.そもそも肥料とは何か?
- 2.知っておきたい!「肥料」の二大分類:化成肥料と有機質肥料
- 【第2章】即効性の土づくり|化成肥料の種類と選び方
- 1.種類豊富な化成肥料:単肥と複合肥料
- 単肥の種類とはたらき
- 複合肥料の種類とはたらき
- 2.化成肥料の環境への影響と注意点
- 【第3章】やさしい畑の土づくり|有機質肥料の種類と選び方
- 1.窒素成分(N)が豊富な有機質肥料
- 2.リン酸(P)が豊富な有機質肥料
- 3.その他の有用な有機質肥料
- 4.有機質肥料と微生物のはたらき
- 【第4章】畑の土づくり応用編|「微生物資材」を活用する
- 1.土を甦らせる微生物資材とは?
- 2.微生物資材が有機質肥料の効果を最大化
- 製品紹介:リサール酵産の複合微生物資材・カルスNC-R 1kg
- 土づくりに関するQ&A
- Q1:家庭菜園のプランターでも土づくりや肥料の使い分けは必要ですか?
- Q2:化成肥料と有機質肥料は混ぜて使っても良いのでしょうか?
- Q3:微生物資材は一度使えば、毎年使い続ける必要はありませんか?
- まとめ:肥料の特性を理解し、たくさんの選択肢を検討しよう
この記事のポイント
- 肥料には大きく「化成肥料」と「有機質肥料」の2種類がある。
- 化成肥料は速効性があり、生育段階でのピンポイント補給に効果的です。
- 有機質肥料は緩効性だが、作付け前の畑の土づくりに欠かせません。
- 微生物資材は有機質肥料の分解を促し、土壌環境を底上げします。
用語解説
| 肥効 | 肥料を与えた結果として作物に現れる生育効果の総称です。栄養素(N・P・Kほか)を供給した成果を指し、葉色が濃くなる、茎葉が伸びる、実が充実するなどの現象が挙げられます。 |
|---|---|
| 土壌改良効果 | 土そのものの性質を良くする作用です。微生物や有機物の働きで団粒構造が進み、水はけ・水もち・通気性が改善し、有用微生物のすみ家も増えます。 |
| 塩類集積 | 塩類集積とは、土壌中の塩類(主に肥料成分)が、水の蒸発に伴って土壌の表面付近に濃く集まりすぎる現象で、主に施設栽培(ビニールハウスなど)において、化成肥料の過剰な施肥と、雨による洗い流し(流亡)の不足によって引き起こされます。 |
畑の成功は、「肥効」で足りない栄養を補うことと、「土壌改良効果」で土の体力を高めることを両輪で回すことにあります。
その肥料の使い方で大丈夫?畑の土づくりを見直そう
収穫量が伸び悩む、葉が黄化する、実つきが悪い……そんなときにはつい肥料の量を増やしたくなりませんか。しかしそれらの症状の裏側には、pHの偏り、塩類の蓄積、団粒構造の崩れ、微生物の減少など、畑の土づくりに関わる原因が潜んでいることが少なくありません。
連作障害や病害虫、欠乏・過剰症に関しても、多くは畑の土づくりに起因します。肥料をどう選び、いつ、どれだけ、どのような形で与えるか……その判断には、基礎の理解が不可欠です。
ここで一度立ち止まり、畑の土づくりと肥料の基礎を学び直しましょう。仕組みが分かれば、過不足のない施肥設計ができ、畑の“体調”も目に見えて整っていきます。
【第1章】土づくりの基礎|肥料の定義や種類とは?

ここからが本編です。まずは出発点である畑の土づくりについて見ていきましょう。
1.そもそも肥料とは何か?
「肥料」とは、植物の栄養に供する、または土壌に化学的変化をもたらす目的で施す物質と法律で定義されています(肥料取締法第2条第1項)。さらに、日本では「肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)」に基づき、肥料の表示や成分、品質・安全性が厳格に定められているのです。
現代は、同一の畑で同じ作物を毎年作ることも多く、自然界のゆったりとした養分循環に比べて、養分の持ち出しが大きくなります。その結果、土壌は徐々に疲弊し、連作障害や欠乏症・過剰症を招きやすくなります。だからこそ、計画的な施肥で栄養を補いながら、同時に土壌改良を進めることが不可欠です。肥料は、現代の畑を安定生産へ導くための必須アイテムなのです。
2.知っておきたい!「肥料」の二大分類:化成肥料と有機質肥料
| 分類 | 化成肥料 | 有機質肥料 |
|---|---|---|
| 主な原料 | 鉱物資源など無機質原料を化学的に合成・加工。 | 油かす、魚粉、家畜糞など、動植物由来の有機物。 |
| 肥効の特性 | ・即効性が高い。 ・安定した品質で供給可能。 |
・緩効性だが効果が長い。 ・供給量や品質が不安定。 |
| 土壌改良効果 | ほとんどなし | あり。(土壌の物理性や生物性を改善することがある。) |
肥料は原料によって「化成肥料」と「有機質肥料」の2種類に大別できます。まずこの大枠を押さえると、選択の精度が一気に上がります。
化成肥料は無機原料を化学的に加工したもので、速効性・品質の均一性が強み。一方、有機質肥料は動植物由来の資材で、緩効性であるものの土壌改良効果を併せ持ちます。
以下の比較表(原料・肥効特性・土壌改良の有無)を手元に保存し、畑の目的と時期に応じて使い分けましょう。基肥の骨格は有機質肥料、緊急の追肥は化成肥料、といった組み立ても賢い使い分けです。
【第2章】即効性の土づくり|化成肥料の種類と選び方
化成肥料は養分を無機態で含んでおり、水に溶ければすぐ吸収されます。生育段階に合わせた狙い撃ち施肥が可能です。
1.種類豊富な化成肥料:単肥と複合肥料
化成肥料は、無機物を原料にした肥料の総称です。単肥はN・P・Kなど一成分に特化したもので、複合肥料は二成分以上を配合したものを指します。
土壌診断や生育ステージを見ながら、足りない成分だけを素早くかつきめ細かく補えるのが化成肥料の強みです。特に小面積の菜園では、必要最小限を適期・適量で使うのがポイントとなります。
単肥の種類とはたらき
| 肥料の種類 | 主な例 | 主なはたらき |
|---|---|---|
| 窒素肥料(N) | ・硫安 ・尿素 ・石灰窒素 など |
葉や茎の成長を促進。生育が停滞した際の追肥として使われるものが多い。 石灰窒素は、センチュウや雑草を防除する効果も期待できる。 |
| リン酸肥料(P) | ・過石 ・熔リン など |
生育初期に根の発達を促進する。また、花や実のつきを良くする。そのため基肥として使用する。 |
| カリ肥料(K) | ・硫加 ・塩加など |
開花・結実に効果を発揮しやすい。基肥としてはもちろん、実をい肥大させたい時期の追肥にも使われる。 |
単肥は“ピンポイント補給”の切り札です。いくつか種類がありますが、主に以下のようなものがよく使われます。
・窒素肥料(N):硫安・尿素・石灰窒素など。葉茎の伸長や葉色改善に向いており、石灰窒素はセンチュウ・雑草抑制の副次効果が期待できます。
・リン酸肥料(P):過リン酸石灰・熔成リン肥など。根の発達、花芽形成・結実を促進し、主に基肥で効かせます。
・カリ肥料(K):硫酸カリ・塩化カリなど。糖・でんぷん合成や倒伏防止に適しており、基肥・追肥ともに使いやすいです。
複合肥料の種類とはたらき
複合肥料は、2つ以上の成分をバランス設計で配合した肥料で、一般に化成肥料とも呼ばれます(厳密には製法で呼称が異なります)。NPK比が明記され、基肥の骨格を手早く作るのに便利です。これに似たものとして、単肥を物理的にブレンドした配合肥料もあります。
両者とも面積あたりの散布量が少なくて済み、ムラが出にくいのが利点です。家庭菜園では、NPK=8-8-8や10-10-10といった総合配合を常備し、作物に応じて微量要素入りを選ぶという方法がおすすめです。基肥は複合で“土台”を整え、必要に応じて単肥で微調整する組み合わせで柔軟な土づくりができるようになります。
2.化成肥料の環境への影響と注意点
化成肥料の速効性は魅力的ですが、入れ過ぎは禁物です。化成肥料の多用は塩類集積を招いて根を傷め、微生物活性の低下や団粒構造の崩壊につながる場合があります。水に溶けた養分が表層に偏在すると、浸透圧の問題で水分吸収が阻害されることもあります。
さらに、吸収されなかった肥料が河川・地下水に流出すれば水質悪化の一因になり得るため、注意が必要です。とはいえ、化成肥料は悪ではありません。適量・適期・適所で使い、有機質肥料や堆肥・微生物資材と併用して、長期的に健全な畑を守りましょう。
【第3章】やさしい畑の土づくり|有機質肥料の種類と選び方

有機質肥料は、動植物由来の有機物を原料とする肥料です。栄養補給だけでなく、微生物のエサとなって土壌改良を同時に進められる点が特徴といえます。速効性は控えめですが、効きが穏やかで持続し、土の保肥力と団粒化を育てます。
ここからは、有機質肥料について、成分別に代表例を確認しつつ、肥料の選び分け方を整理します。
1.窒素成分(N)が豊富な有機質肥料
窒素(N)は葉・茎の生育を助ける成分です。以下のようなものがあります。
・油かす:菜種・大豆などの搾りかすです。分解はゆっくりで、持続性のある窒素資材といえます。未熟堆肥を多用するとガス障害の恐れがあるため完熟堆肥と併用が無難です。
・魚かす(魚粉):乾燥・粉砕した魚由来資材です。油かすより分解が早めで、初期生育の立ち上がりを助けます。リンや微量要素も含み、実ものにも相性がいいです。
・鶏糞:家畜ふんの中ではN濃度が高めで、比較的即効性があります。ただし塩分やpH上昇のリスクがあるため、用量を守り、土の反応を観察しながら使うことが重要です。
2.リン酸(P)が豊富な有機質肥料
リン酸(P)は根の発達と花・実つきを促します。
・蒸製骨粉:動物の骨を蒸して粉砕したものです。緩効性で根圏にじわりと効きます。
・米ぬか:入手しやすくゆっくり土に分解されます。窒素も少量含み、土壌微生物が活発になります。すき込みは少量からが安全です。
3.その他の有用な有機質肥料
以上でご紹介したもののほかにも以下のような有機肥料があります。
・草木灰:Kが豊富でpH矯正にも寄与します。使いすぎるとアルカリ化するため控えめにしておきましょう。
・カニ殻:キチンを含み、土壌中の微生物相に良い影響を与えて病害軽減が期待できます。
・堆肥:家畜ふん・稲わら・落ち葉などの発酵資材です。団粒促進と栄養供給の両面で、広義には“有機質肥料”として機能します。作付け2~3週間前に完熟をすき込みましょう。
4.有機質肥料と微生物のはたらき
作物は有機物を直接吸収できません。土中微生物が有機物を分解(無機化)してはじめて、根が吸える形(硝酸、アンモニウム、可給態リンなど)になります。つまり有機質肥料は微生物のエサでもあります。
土の微生物環境が整っていないと分解が遅れ、肥効が現れません。だからこそ、微生物が働ける条件(適切な水分・pH・酸素、そして有機物供給)をセットで整えましょう。
【第4章】畑の土づくり応用編|「微生物資材」を活用する
微生物資材は、有機の分解を後押しし、土の生物性を高める定番商品といえます。うまく活用すれば、畑の回復力が段違いになります。
1.土を甦らせる微生物資材とは?
微生物資材は、有用微生物(細菌・糸状菌・放線菌など)を目的に合わせて高濃度培養し、畑に施用できる形にしたものです。直接栄養を与えるのではなく、分解・無機化・拮抗といった微生物の働きを強めることで、間接的に作物の生育を支えます。
微生物が育てば団粒形成が進み、作物の根が伸びやすくなり、病原菌の入り込みにくい土に近づきます。
2.微生物資材が有機質肥料の効果を最大化
植物は有機物をそのまま吸収できません。分解の主役は微生物です。土には2~3μm級の細菌から、肉眼で見える微小生物まで、さまざまな生き物が暮らしています。微生物資材は、その微生物たちを畑にダイレクトに補給する考え方にもとづいて作られています。
微生物資材によって活性化すれば、分解スピードが上がり、可給態養分が切れにくくなるのです。さらに、有用菌が優位になると、病原菌の居場所が減って発病リスクも下がります。
有機質肥料とセットで運用すれば、「効果の緩効性+安定供給」が両立し、肥料の効果を最大化できます。
製品紹介:リサール酵産の複合微生物資材・カルスNC-R 1kg
小規模農家・家庭菜園ユーザーにおすすめしたいのが、リサール酵産の「カルスNC-R 1kg」です。複数の微生物をバランスよく組み合わせた複合微生物資材で、空気の多い表層から少ない深層まで、分解の“すき間”を埋めることができます。
有機質肥料や残渣と併用すると、分解→無機化→団粒化がスムーズに進み、ふかふかで保肥力の高い土へと育ちます。特に1kgタイプは小面積でも使い切りやすく、保管もしやすいため、初導入に最適です。
使い方は、作付けの1~3週間前に有機質肥料・完熟堆肥とともに均一散布し、すき込みます。まずは一畝分の試験区で、立ち上がり・根張り・水はけの違いを観察し、好感触なら面積を段階的に広げましょう。
化成肥料の投入量を抑えたい方、連作障害や土の締まりに悩まれている方に、特におすすめです。
土づくりに関するQ&A
この章では、特に家庭菜園をされている方や、肥料の使い分けに悩む方々が抱きやすい具体的な疑問に、Q&A形式でお答えします。プランターの土の扱い方から、化成肥料と有機質肥料の賢い併用方法、そして微生物資材の継続的な必要性まで、あなたの疑問を解消し、より実践的な土づくりをサポートします。
Q1:家庭菜園のプランターでも土づくりや肥料の使い分けは必要ですか?
A1:はい、必要です。プランターは土量が少なく、水やりで養分が流れやすく、有機物が不足しがちです。まずは新しい培養土+完熟堆肥(少量)+有機質肥料(控えめ)を基本形にし、植え付け2~3週間前に微生物資材を加えて土の立ち上がりを早めます。
生育途中は、葉色や徒長の有無を観察しながら、化成肥料の少量追肥で微調整しましょう。作が終わったら、ふるい・天日干し・堆肥混和でリフレッシュし、2~3作ごとに全面交換を検討すると、土疲れを防げます。
Q2:化成肥料と有機質肥料は混ぜて使っても良いのでしょうか?
A2:併用は非常に有効です。初期は化成肥料の速効性で立ち上げ、中盤以降は有機の持続性で支えるという流れがベストです。
ただし、化成肥料の入れ過ぎで塩類集積とpH上昇を招かないこと、有機質肥料を入れたら微生物が働ける条件(水分・酸素・温度)も整えることを意識してください。土壌診断があればそれにもとづいて精密に調整し、なければ少量・こまめを合言葉に運用しましょう。
Q3:微生物資材は一度使えば、毎年使い続ける必要はありませんか?
A3:継続的な施用が望ましいです。土の微生物相は、耕起・乾湿・施肥・収穫などで常に変化していますので、せっかく立ち上がった有用菌優位の環境も、時間とともに揺らぎます。
毎作の有機質肥料・堆肥と微生物資材をセットで取り入れることで、分解・無機化のサイクルが安定し、連作障害のリスクを下げられます。まずは作付け前の基礎投入、必要に応じて定植時の局所投入という二段構えがおすすめです。
まとめ:肥料の特性を理解し、たくさんの選択肢を検討しよう

即効性が高い化成肥料で今必要な栄養を補い、有機質肥料でゆっくりと土壌改良していくことで、「畑の体力」を底上げできます。化成、有機質どちらが正しいというものはなく、特性を理解して使い分けることが肝心です。
さらに、微生物資材を使えば有機の分解を促し、団粒構造と保肥力を育て、肥料の効果を最大限に引き出すことができます。目的とする品質・収量・省力・環境に合わせて選択肢を広げ、診断→計画→施用→観察→調整のサイクルで畑を育てていきましょう。今のひと手間が、来季の安定収穫とおいしさにつながります。